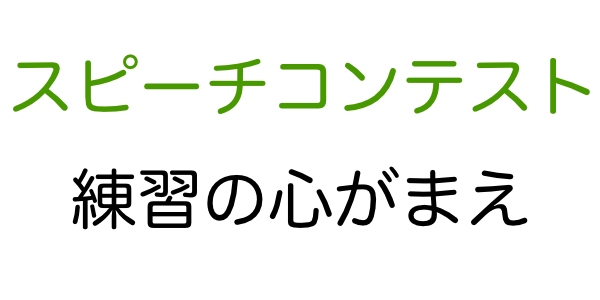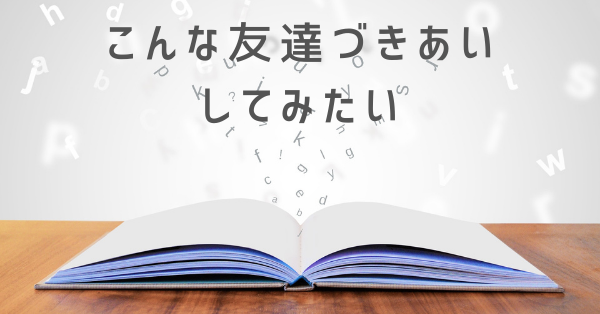ちくま学芸文庫から、『中国語はじめの一歩(新版)』(木村英樹・著)という本が出ました。
ちくま新書で出版されていたものが加筆修正を経て学芸文庫入りしたものです。

大学生だったとき、この『中国語はじめの一歩』を読んで、体の底からわき上がってくるようなゾクゾク感を覚えました。
冒頭は、木村先生の第1回目の授業を模した語り口調で始まります。中国語を学んだことのない人でも聞いたことくらいはある、「ウォー・アイ・ニー」(我爱你)を例にとり、“我、你、他、爱”だけで6通りもの文が作れることを解説してくれます。
この第1回目の授業だけで、中国語の孤立語としての特性が十分に伝わりますし、「中国語ってとっつきやすそうだ」とか「日本人には親しみやすそうだ」という期待感も与えてくれるという、映画の予告編のようなわくわくを与えてもらえます。
しかし、読み進めていくうちに、読者は一気に中国語の深層にまで引き込まれていきます。
入門の時期というのは、与えられる文というのも単純そのもので、そこには何の不思議もないような気がします。
でも、「言われてみればそうだよな」と気付かされることの、なんと多いことか。
たとえば、日本語では王貞治(例がやや古いですが)がホームランを打つことを、「王はホームランを打つ」とも、「貞治はホームランを打つ」とも言えます。
いっぽう、中国語では“贞治打本垒打”(“本垒打”は「本塁打」)とは言えますが、“王打本垒打”とは言えません。
これは、中国語では姓は固有名詞としてははたらくことができず、“王”は〈王〉という一族を指す「類称」である、と説明されています。
確かに、中国人が姓を単独で使うことはほとんどありません。必ず個を特定するために、“老/小”(〜さん/〜ちゃん)をつけたり、フルネームで呼んだり“王总”(王社長)と肩書をつけて呼びます。(でも、わたしの知人の在日中国人は、なぜかお互いのことを“张”とか“郭”とか呼び合っています。これは日本語の影響を受けたのかな…?)
ほかにも、“三毛八分钱”(「三毛八分」のお金)という表現を例に取り、このように説明してくれています。
日本語では、時刻の表現と同様、お金も〈もの〉を〈数える〉タイプの表現では数えません。「(ギョーザは)45円です」とは言っても、「(ギョーザは)45円のお金です」とは言いません。しかし中国語では時刻もお金も、“一条鱼”(1匹の魚)と同様に、〈もの〉を〈数える〉かたち、すなわち「数詞+量詞+名詞」で表現されます。(p154)
慣れてくると、“三毛八分钱”に違和感など覚えなくなりますが、言われてみれば確かにそうなのです。
ほかにもほかにも、なぜ中国のバス停・駅名は“人民大学前”といわずに“人民大学”などと、隣接する施設そのものの名称がつくのか、といった問題にも分析の光が当たります。日本だと、「県庁前」だとか「明大前」だとか、必ずといっていいほど「○○前」になりますよね。「名古屋大学」駅などの例外はありますが。
確かに、自分が初学者のころに「アレッ」と思ったり、あるいは、教室で教えていて学生が引っかかっていることを何度も目にしてきたはずなのです。
自分が一体どれだけの「宝」を落としてきたのか、嘆きたくなってくるくらいです。
「はじめの一歩」と銘打たれている一冊ですが、その一歩のなんと大きなことか。
「はじめの一歩」というタイトルに吸い寄せられた初学者は、はじめはメリーゴーラウンドに乗るように、ニコニコしながらお客さん気分で読み始めることでしょう。
しかし、読み進めるに従って、自分がジェットコースターに乗せられていたことに気づくはずです。
教科書や入門者向け参考書などでは何の解説もないような単純な言語現象、その背後に横たわる中国語の本質を突きつけられて「言語ってすごーい!」「文法ってたーのしー!」という驚き、興奮とともに本を閉じることになると予言します。
木村英樹先生の『中国語はじめの一歩』(ちくま学芸文庫)を購入しました。新書版を繰り返し読んだので、加筆修正を経た最新版を読めるのがとても嬉しい。中国語学習者は必読の一冊。
意図してのことでしょうが、帯がなんかインチキ中国語っぽい 笑https://t.co/o18X5InN4x pic.twitter.com/EeztNnfQ2n— 岡本悠馬 (@yuma_okamoto) 2017年6月7日
帯がなぜかインチキ中国語。