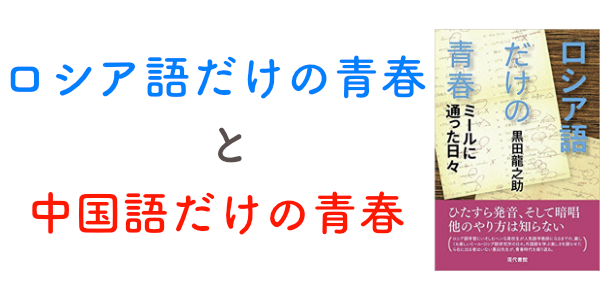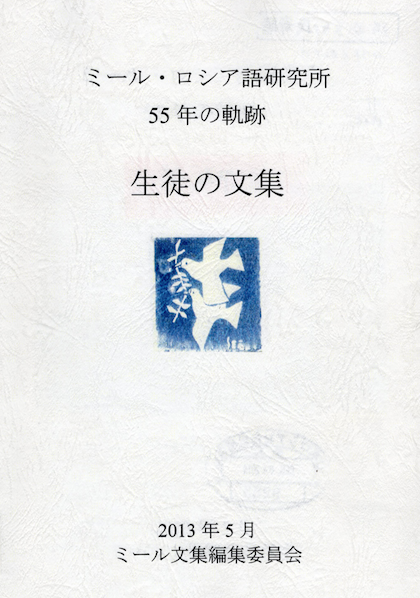
ずっと読みたかった本を手に入れました。
正確に言うと、借りることができました。
『ミール・ロシア語研究所 55年の軌跡 生徒の文集』という冊子です。
ISBNもバーコードもついていない、非売品です。
1958年に東一夫氏によって創設され、2013年に同じく講師である妻の多喜子氏の引退によってその幕を閉じた、知る人ぞ知るロシア語教室です。
私は、黒田龍之助先生の著作でこの教室の存在を知りました。
『その他の外国語』というエッセイで、「ロシア語学校M」として紹介されていたのです。
そこにはこう書かれていました。
少し長くなりますが、引用します。
Mでは発音がすべてである。
授業では教科書の例文をひたすら音読する。
クラスには通常5〜6人の受講生がいるが、90分の授業のうち、3分の2はテープのあとについて一人ひとりが順番に発音する。
このときに先生から発音を厳しく直される。
一つひとつの音だけでなく、アクセントの強さやイントネーションまで含めて、一つの文を何度も読み直すよういわれる。
一度でハラショーといわれることは滅多にない。
文法はとくに教えない。
教科書には文法説明もロシア語に対する和訳もすべて書いてある。
質問があればできるが、ここでは別のことに時間を使ったほうがいいことを、みんな分かっている。
(中略)
人は自分の学習方法が基本となる。
わたしの基本はこのMで学んだ方式であった。
発音を疎かにしないこと。
文をひたすら暗唱していくこと。
この2点に集約される。
あとははっきりいってどうでもいい。
外国語学習には設備もたいしていらない。
いまではさまざまな語学学習器材があるのに、テープレコーダー以外はほとんど使わないで授業しているのも、こんなことに原因がありそうだ。
私は外国語大学の学生だった頃にこのエッセイを読んで、心底うらやましくなりました。
「こんな教室で勉強してみたい!」と真剣に思いました。
発音を非常に大切にする、という点は、私の母校の中国語の指導方針にも通ずる部分があり、私にもその考え方が違和感なく受け止められたのです。
中国語が上手くなりたくて、大学以外にもいくつか教室に行ったりしましたが、こんな教室にはめぐり逢うことができなかった。
仕方がないので、自分で教材を選んで、ひたすら音読、ひたすら暗唱を繰り返しました。
だから、間接的には自分はミール・ロシア語研究所の生徒だと思っています。
2013年にミール・ロシア語研究所が閉鎖されることになり、そこで学んだ生徒たちが教室での思い出をつづったのがこの本です。
ネット上でこの本の存在を知り、「読んでみたい」という気持ちがむくむくとわき上がってきました。
自分の外国語学習に何かヒントになることはないか。
教える立場になったいま、何か示唆をもらうことはできないか。
何しろ、もう教室はないのですから、いまからロシア語を始めてもミールに通うことはできません。(実はかじったことはある)
この冊子だけが手がかりです。
そう思って、あれこれ手続きをして、ようやく念願叶って、少しの間だけ私のところに預けていただきました。
冊子は約150ページあり、前半50ページは教室の記録、後は約100ページにわたり、生徒さんたちの思い出がびっしりと書かれています。
ちょっとだけ引用します。
入門科と予科ではとにかく「音を作る」というのが多喜子先生から与えられた至上命題であった。
どの外国語学習にも言えることだが、日本人が外国語としてロシア語の獲得を目指す際に、ロシア語の「音を作る」ということは実に重要な作業である。
「音を作る」この一言がすでにミールの教育の特徴をよく語っていると想う。
ご夫妻は非常な使命感をおもちで、生徒をとても大事にされたが、甘い顔はけっしてみせられず、人に媚びるということがなかった。
生徒もその意気に感じ、必死にがんばる人が多かったと思う。
ミールでは3か月おきにテストがあり、それまでに習った文章をすべてロシア語で覚えて臨まなければならない。
前日はもちろん徹夜で、当日の昼間の仕事中も、暇を見つけてはトイレにこもり、ぶつぶつとロシア語を呟きながら夕方の試験に備えていた。
読んでいると、まるで自分もその教室の生徒になったような気がしてきます。
まだまだ甘い勉強をしているなあ、と少し恥ずかしくなります。
私が自分の教室を厚かましくも「南天中国語”研究所”」と名付けたのは、ミール・ロシア語研究所にあやかってのことです。(2020年に「南天中国語ラボ」に改称)
ちょっと分不相応な自分の教室名を見るたびに、少しでもそこに近づくことができたらと思っています。