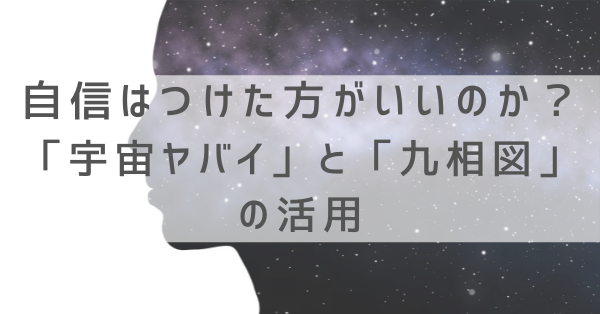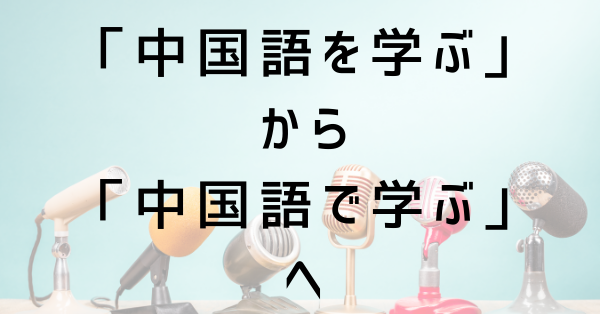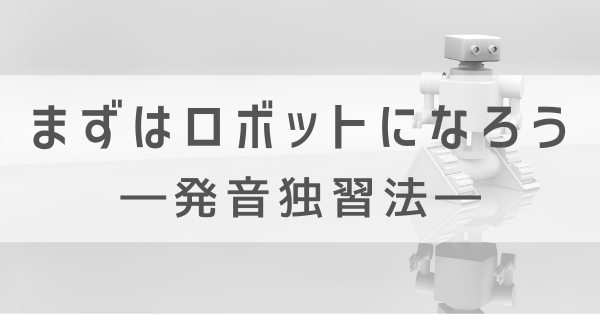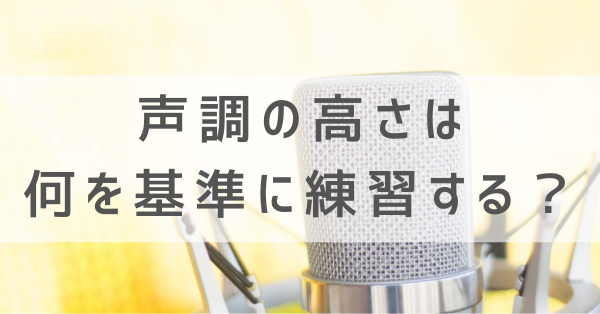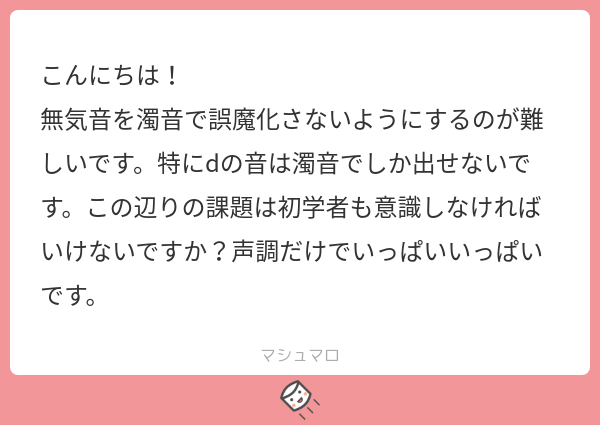
こんな質問が来ました。
久しぶりにブログ記事でマシュマロにお返事いたします。
結論から言うと、「声調だけでいっぱいいっぱい」なのであれば、今は無気音を濁音でごまかしてしまってもかまいません。
しかし、「2声がどうしても出ない」とか「無気音が有気音になってしまう」といった問題は、ちょっと深刻です。
なぜなら、間違って出すことで意味が変わってしまったり、通じなくなってしまうことがあるからです。そのまま直さずに放置していると、早い段階で進歩が頭打ちになるからです。
一方、無気音が濁音になってしまっても、それによって別の音に聞こえてしまうことは(多分)ありません。
“d”が「だ行」に、“g”が「が行」になってもいいのです。まあ、多少不自然に聞こえるかもしれませんが、いいじゃないですか、ガイジンなんですから。
学習がある程度進んで、余裕が出てきたときに「もうちょっとキレイな音で発音したいな」という意欲が出たときに対処してみればいいのです。
無気音が濁音になってしまう癖を直すのは、そう難しいことではありませんから、そのときにどなたかにお願いしてみれば、20分もあれば正しい方向に導いてもらえます。
あるいは、その頃にはご自身の中国語を聴く耳も育ってきて、自分で矯正できてしまうかもしれません。
ということで、まとめますと、結論は以下のとおりです。
・聞き手の誤認を生む、通じなくなってしまうような癖は妥協せずに直しておく。(例:声調、有気音・無気音の区別)
・多少不自然でも通じるものは、後回しでかまわない。(例:無気音が濁音になる、anとangがごっちゃになる等)
でも、二者がはっきり明確に区別できるわけではありません。仮に声調が間違っていたとしても、実際の意思疎通の場面では、なんとか押し通してしまうことも可能だからです。
「でも、とりあえず最低ラインとして、声調だけはなんとかしておきましょう」というのがわたしからの提案です。